top of page
検索


再会 <56> いちご味のイタリア地葡萄
Ferdinando Principiano, Langhe Freisa 2022. ¥3,500 イタリアのマイナーな地品種を学ぶのは、この上なく楽しい。 フランス系国際品種や、イタリアの中でもより王道と言えるネッビオーロ、サンジョヴェーゼ、アリアニコなどとは随分毛色の違う個性派集団。 どの品種をとっても「洗練」とは少々遠く、自己主張が激しめなのも良い。 まるで、予定調和的な美意識を嫌い、「絶対にアルマーニなど来てやるものか!」っと、こちらから聞いてもいないのに声高に叫んでいる、ちょっとうるさいイタリア人のようだ。 そして、 イタリア各地のマイナー地品種それぞれに、豊かなストーリーがある ところも良い。

梁 世柱
2024年3月10日


出会い <55> 最高のメルロー
Chiacchiera, Piccola Viola 2021. Wine Memo <19> で述べたように、国際品種がブレンドされた一連のChiantiやVino Nobileに対して、私が異を唱え続けることは今後も変わらないだろう。 サンジョヴェーゼとその他の補助的地品種だけで構成されたワインの、調和に満ちた優美な味わいを思えば、国際品種による補強が「伝統の進化」とはどうにも思えない。 ワインにとって「美味しい」ことは正義だと思うが、それが 伝統かと問われれば話が違う のだ。 一方で、国際品種のみで造られたワインに素晴らしい「品質」のものが数多くあるのもまた事実なので、そ の探究は私にとって隠れた趣味的なもの となっている。

梁 世柱
2024年3月3日


再会 <55> 微笑んでしまうワイン
A.A.Badenhorst, Kalmoesfontein White Blend 2021. ¥6,800 思い出が甦ってきてついつい笑ってしまう、そんなワインがある。 ワイン産地では、大なり小なり楽しい思い出はあるものだが、大抵の場合、適度に緩く、明るい国民性や地域性を通しての体験が、そうさせるものだ。 そしてなぜか、私にとって「笑ってしまうワイン」の多くが、 南アフリカ にある。 一年半前に初めて訪れた南アフリカでは、数多くの造り手たちと、談笑と爆笑のひと時を過ごした。かなり暗く辛い歴史がある国だが、少なくともワインに携わっている人々は、肌の色に関係なく、笑顔でいっぱいだった。 地域によっては、造り手たちも、試飲会の後半にでもなるとすっかり酔っ払っていて、ブースを飛び出してはしゃぎ回っている。 最初は驚いたが、すぐに慣れた。私自身は間違いなく「おとなしい」部類の人間だが、声を上げて歌い、踊っている彼らをみるのは、なんとも清々しいものだ。 異文化の中に身を置くことでしか体験できないグルーヴ が、そこには確かにある

梁 世柱
2024年2月26日


Wine Memo <20>
Cinciano, Bianco Preziano 2023. ブラン・ド・ノワール というのは、何もシャンパーニュの専売特許というわけではない。 他産地のスパークリングワインに、(シャンパーニュ方式であるかどうかに関わらず)ブラン・ド・ノワールが採用されることは昔から多々あるし、さらに近年では、もはや そもそもスパークリングですらないことも多いに増えてきた 。 ブラン・ド・ノワールのスティルワインが増えた背景としては、ワインスタイルの多様化と自由化、そして地球温暖化が主な理由として考えられる。 私もそれなりの興味をもって、様々な国の様々な黒葡萄から造られたブラン・ド・ノワールを試してきたが、それらは 「消極的」と「積極的」 なブラン・ド・ノワールに大別することができる。 消極的 、と書くと随分イメージが悪くなるかも知れないが、こ のタイプは基本的にシャンパーニュ方式の流れを組んでいるもの となる。

梁 世柱
2024年2月21日


出会い <54> 最強のブルゴーニュ・キラー
J ür g, Spätburgunder G.G. “Sonnenberg KT” 2019. ¥7,800 2024年に入ってから、ブルゴーニュ関連のマスタークラスを立て続けに開講していることもあり、例年以上に深く彼の地と向き合う日々が続いている。 ソムリエ駆け出し時代から、 マット・クレイマー著の「ブルゴーニュが分かる」 や、 クライヴ・コーツMW著の「The Wines of Burgundy」 といったブルゴーニュ関連の名著は、擦り切れるほど読み込んだし、ブルゴーニュが飲める試飲会には積極的に足を運び、プライヴェートでもヘソクリを絞り出して、グランクリュに手を伸ばしてきた。 私の頭の中には、自分でも不思議に思うほど膨大なクリマ名や、そのワインの特徴に関するメモリーがアーカイヴされている。 私はそもそも、物忘れが極端に激しく、カレンダーに詳細に書き込んだスケジュールやSNSでの「名前と顔の照合」を頼りに、日々をなんとか重大なトラブルなく生きているようなタイプの人間なのだが、きっとそうなってしまったのは、限られたメモリー容量

梁 世柱
2024年2月18日


Wine Memo <19>
Ca di Pesa, Serafino 2021. 今年もまた2月の トスカーナ にやってきた。 ニューリリースを祝う アンテプリマ展示会 だ。 6日間ほど、ひたすらサンジョヴェーゼの海を泳ぎ続ける日々は実に楽しいが、なかなか辛くもある。 若いサンジョヴェーゼをテイスティングし続けるのは、実際にかなり骨が折れる。 数時間テイスティングすればもう、強い色素で完全にお歯黒状態となり、強烈な酸の刺激で舌が痺れ、分厚いタンニンが歯茎にびっしりとへばりつく。 初日の緩いレセプションを終え、今年のアンテプリマは キアンティ・クラシコ からスタートした。 私はキアンティ・クラシコが大好きなのだが、 少々偏った「好み」 がある。 そう、カベルネ・ソーヴィニヨン、メルローなどがブレンドされたクラシコが、とにかく好きでは無いのだ。(このタイプのクラシコは、明らかに減少傾向にある。)

梁 世柱
2024年2月16日


再会 <54> 熟成ナチュラルVinho Verde
Aphros, Ten 2012. Vinho Verdeは高い長期熟成能力を有する。 その事実は、先日レポートしたSoalheiroにおける大垂直テイスティングでも、Vinho Verde特集記事後編で紹介した、Sem Igualにおける垂直テイスティングでも確認することができたが、果たして ナチュラル志向なワインの場合 はどうだろうか? ナチュラルワインの長期熟成能力は、適切な(時に過剰な)亜硫酸添加によって守られたクラシックなワインよりも、 ランダム性が強い ことは間違いない。 低アルコール濃度で、高酸度のワインを造ることを目的とした 不用意な早摘み、発酵・熟成時の不適切な管理 、自然の力に対する精緻な観測を無視し、盲目的に信じ込んでいるかのような 亜硫酸無添加 など、「そもそも長期熟成に向いたテロワールと葡萄品種の組み合わせではない」こと以外にも、ナチュラルワインが長期熟成能力を著しく失する要素はある。 一方で、 完全な調和に至ったナチュラル・ワイン は、一般的なクラシック・ワインを遥かに凌駕する、 圧巻の超長期熟成能

梁 世柱
2024年2月11日


出会い <53> ブルゴーニュ生まれのナチュラル「テロワール」ワイン
Domaine Dandelion, Pet’ Nat 2022. ¥5,000 今回はあえて、この言葉を極端な意味合いで使うが、私はかねてから 歴史的大銘醸地 における 「ナチュラルワイン」 に、少々懐疑的な立場をとってきた。 理由は二つ。 まず、ナチュラルワインの中でも 欠陥的特徴の現出 を厭わない 「ワイルドナチュラル」 が、葡萄畑と葡萄のもつ個性をありのままに表現したいという 造り手の想いとは反し 、(往々にして稚拙で極端な)醸造工程によって発生した 欠陥的特徴そのものが、テロワールと呼ぶべきものを相当程度覆い隠してしまう危険性を秘めている からだ。 もちろん、テロワールの精緻な表現よりも、最終的な味わいを自身が「美味しい」と感じることを最優先とするのであれば、問題とはならない。つまり、そこに個人的な「良し悪し」という二元論を他者に押し付けること自体が、「余計なお世話」ということだ。 よって、(クラシックワインと呼ばれるものの相当数も、過度な調整と矯正によって結果的にテロワールを失していることも踏まえ)本稿の内容はあく

梁 世柱
2024年2月4日


再会 <53> 聖地をも超える特異
Sadie Family Wines, Mev. Kirsten 2021. ¥22,000 大航海時代以降、ヨーロッパワインの歴史を彩ってきた ヴィティス・ヴィニフェラ種 は、世界各地へと旅立っていった。 16世紀半ば に、 アメリカ大陸 へと リスタン・プリエト (ミッション、パイス、クリオージャなど、国によって呼び名が異なる。)が渡って以降、最初期は新大陸を目指す長い航海の最終経由点であった、イベリア半島やカナリア諸島の葡萄が持ち出されていったが、やがて西ヨーロッパ諸国の広範囲から、様々な葡萄が選ばれるようになった。 特にボルドー品種、ブルゴーニュ品種、ローヌ品種、そしてアルザス品種(リースリングとミュスカ・ブラン・ア・プティ・グランを意味するが、共に原産地はアルザスではない)などのフランス系及び準フランス系品種はニューワールド各国で勢力を増し、やがて国際品種として確固たる地位を築いた。 各地のテロワールに即した栽培、醸造技術も飛躍的に進歩し、中にはそれぞれの品種のオリジンたる「聖地」をも、(視点次第では)凌駕したとすら言え

梁 世柱
2024年1月28日


出会い <52> 地品種+国際品種
Quinta do Mouro,Tinto 2018. 現地価格39 € 世界には膨大な種類のワインがある。 間違いなく、 一生かけても全てをテイスティングするのは不可能 だ。 だからこそ、私はワイン探求において、超広範囲をカヴァーしつつも、相当程度「 取捨選択 」をしながらテイスティングを重ねている。 どうせ「全てを知ることはできない」のであれば、 闇雲に節操なくテイスティングし続けるよりも、テーマをもって集中的にやった方が遥かに身になる ことは、経験上断言できるのだが、当然ながら、私のレーダーに引っかからないタイプのワインは無数にある。 特にヨーロッパ産のワインであれば、私は優先的に「国際品種系」のワインをテイスティング対象から外す。 地品種から造られたワインにこそ、その地の歴史、伝統、文化が真に宿り、完全にユニークな表現を見出すことができる。 その主張を崩すつもりは毛頭無いし、地品種の魅力は、他に変え難いものがある。 しかし、だからと言って私が国際品種系のワインを低評価しているということでは決してない。

梁 世柱
2024年1月21日
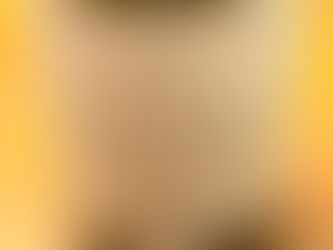

Wine Memo <18>
Bodegas Fulcro, Albariño “A Cesteira” 2021. 昨年12月のVinho Verdeツアーには、日本から2名、イギリスから2名、そしてカナダから8名が招待されていた。 主にソムリエを中心に集められたメンバーだったため、いつもの海外訪問よりは年齢層が低い(海外でも、若いジャーナリストはユニコーンだ。)とは予想してはいたが、カナダから来ていた一人の若者には大いに驚かされた。 職業はモデル、と言われても全く疑わない程の美貌に恵まれた彼女は、なんと21歳。 ソムリエとしても現場に立っているそうだが、彼女はInstagramでフォロワー約29万人を抱える、いわゆる「インフルエンサー」という仕事もしている。 彼女のことを良く知る前は、「なんだ、そういう枠か」と思った(個人的に、ブロガーや自称インフルエンサーなる人々とは、あまり良い思い出がない。)ことを正直に告白するが、ツアーの最中、誰よりも熱心に質問(しかも非常に鋭い!)を繰り返し、テイスティングの際は高い集中力で真剣にワインと向き合い、その知識量は

梁 世柱
2024年1月18日


再会 <52> ブラインドでこそ見える真実
Dom. Vincent Dauvissat, Chablis 1er Cru La Forest 2018. 各種コンクールの盛り上がりもあり、すっかり競技化した側面も強いブ ラインド・テイスティング 。 恐ろしく膨大な選択肢の中から、完全にノーヒントで品種、産地、ヴィンテージ、或いは生産者やキュヴェまで看破して見せるのは、砂漠の中からダイアモンドを探り当てるような作業に等しく、まさしく 神業 とすら言えるだろう。 「ディテールまで当てる」という意味では、その領域に到達できるのは、凄まじい修練を重ねた上で、超スピードの取捨選択を脳内で繰り返すことができる、極々限られたトップ・アスリートのみだ。 例え一割の成功率でも、そのような神業を繰り出せる人を、私は心から尊敬しているが、私自身がブラインド・テイスティングを行うときの最大の楽しみは、「当てること」ではなく 「真実を暴くこと」 にある。

梁 世柱
2024年1月13日


SommeTimes 2023年 ベスト・パフォーマンス賞
2022年末に、「権威の礼賛」からの解放、を2023年のテーマとして掲げた。 今年の現地訪問は、イタリア・トスカーナ州とカンパーニャ州、ポルトガルのダオン、バイラーダ、ヴィーニョ・ヴェルデ、ドウロの合計6産地。(ワインとは関係ないが、台湾の茶産地を含めると9産地。)...

梁 世柱
2023年12月24日


出会い <51> リスボンの熱狂
Marinho Vinhos, Tube Tinto 2020. もちろん例外は多々あるが、全体論で言うと、田舎よりも都会の方が、オーガニックやサスティナビリティに対する意識が高い人たちは多い。 田舎の人たちに言わせて見れば、都会人は自分で農業をやっていないから、オーガニック化する大変さを知らない(まさに私自身がそうだ)とか、経済的に余裕があるから多少物価が上がっても問題ないとか、色々と意見が出そうなものだが、都会の人は外側から好き放題言うものだし、購買力も高いので、結局田舎の人たちは都会の意見を無視しきれなくなる。 あまり健全とは言い切れない このあたりの関係性には、私もアカデミックな意味で強い興味をもっているが、都会の近くにあるワイン産地が、都会人のサスティナブル思考に強い影響を受け、 急速にその姿を変化させていく ことは、少なからず世界各地で起こっている。 古い例だと、 サン・フランシスコに近いナパ・ヴァレー が該当するし、比較的新しい例だと バルセロナに近いペネデス や、 メルボルンに近いアデレード・ヒルズ などが該当する

梁 世柱
2023年12月17日


再会 <51> 二次市場の功罪
Dom. Armand Rousseau, Grand Cru Clos de la Roche 2014. 転売ヤーなる言葉が一般化した現代だが、ワインにおける転売(もしくは熟成後に高値で販売)、そしてその主戦場となる 二次市場 の歴史は古い。 ボルドーのネゴシアン は、まさにその 古典的な例 。 大雑把に説明すると、ボルドーのネゴシアンとは、プリムール価格で大量に購入したワインを自社倉庫で熟成させ、適切なタイミングを見計らって、時価でリリースする、という組織だ。 マーラー・ベッセ社 など、その熟成コンディションに定評のあるネゴシアンなら、ある程度のプレミア価格も、自身で熟成管理する手間やコストを考えれば、十分に納得いくものであることは多い。 特に、店舗外に倉庫を構えることができない小規模店舗にとって、名門ネゴシアンは、ありがたい存在であり続けてきた。 このような仕組みが昔からあったワイン市場だが、 ロバート・パーカーJrによる100点法 で、 二次市場が劇的に活発化 して以降、その混迷は深まるばかりである。

梁 世柱
2023年12月10日


Wine Memo <17>
Quinta do Soito, Dão Espumante 2019. 私は世界中のありとあらゆるスパークリング・ワインの中で、 シャンパーニュ が最も好きだ。総合力で見れば、 最も優れている 、とも思っている。 散々権威主義的ワイン道に否定的な立場を取りながら、結局シャンパーニュか、と後ろ指を指されても仕方ないかもしれないが、「 良いものは良い」 と、どこまでも フラット であり続けることこそが、私なりのバランス感覚である。 しかし、高価なシャンパーニュを日常的に飲むことはできないので、 シャンパーニュ・オルタナティ ヴは常に探している。 優れたものに出会えば、心踊る気分にもなる。 特に最近強い興味をもっているのは、シャンパーニュ品種ではなく、 地葡萄を使用したタイプ のもの。

梁 世柱
2023年12月9日


出会い <50> Dirk’s Children
Carlos Raposo / World Wild Wines, Touriga Nacional “Impecável” 2021. ○○’s Children (○○の子供達)、というワイン業界で時折目にする表現は、意外と古くからある。 最も有名なところだと、シャンパーニュ地方のスーパースター集団となった、 Selosse’s Children あたりが思い浮かぶ。 Selosseとはつまり、レコルタン・マニピュラン(もはや死語か?)の頂点として崇められた、Domaine Jacques Selosseの当主 アンセルム・セロス のことを指し、Selosse’s Childrenは彼の弟子達ということになる。 ジェローム・プレヴォ、ユリス・コラン、ベルトラン・ゴートロ、アレクサンドル・シャルトーニュ、ミシェル・ファロンなど、オープンな性格のアンセルムが受け入れた弟子達の名は挙げればキリがないが、その錚々たるメンバーを見る限り、もはや粒揃いどころの話ではない。 他にも、同じくフランスでは、 Marcel’s Children (ボジョレー地

梁 世柱
2023年12月2日


再会 <50> 世界が求める日本人のワイン
Kusuda Wines, Pinot Noir “Martinborough” 2017. 大阪のお好み焼きと、広島のお好み焼き。 どちらが優れた料理か。どちらが本物か。 私の答えは、迷うことなく「大阪」となる。 その理由は、ただ一つ、私が大阪で生まれ育ったからだ。 「同郷バイアス」 とは、我々が意識している以上に強力で、冷静な品質判断などは、いとも簡単に「不必要なもの」となってしまう。 そう、そこに必要なのは、感情からくる全面的な肯定だけなのだ。 私自身はその同郷バイアスを強く認識しているため、日本が関連したあらゆるワインに対して、徹底して感情移入を排してきた。 しかし、それは同時に 「逆張りバイアス」 がかかってしまう可能性を生んでいるのも事実だ。 つまり、感情移入を拒絶するが故に、重々気をつけていなければ、無意識に批判的な視点から見てしまいかねない、ということ。 だからこそ、私は同郷バイアスがかからない、 海外プロフェッショナルの意見 を求めることが多い。

梁 世柱
2023年11月25日


Wine Memo <16>
Luis Seabra Vinhos, Alvarinho Granito Cru 2021. 全体論 で言うならば、ポルトガル・ワインの中でも私の興味レベルが最も低いのは、 ヴィーニョ=ヴェルデ だろうか。 アルコール濃度が低く、非常に軽く、薄く、極微発泡性で、低価格の超大量生産型ワインという典型的なヴィーニョ=ヴェルデは、どうにも私の心の琴線に触れない。 そういったワインの「役割」は十分に理解もリスペクトもしているが、最大公約数的味わいも、その造り方も、私にそのワインを堪能したいという欲をもたらしてはくれないのだ。 私はそのようなワインを、 「Soulless Wine(魂の抜けたワイン)」 と度々表現しているが、魂が(技術の過剰な駆使などによって)極限まで薄められたワインが私に響かないのは、私が魂を宿した存在である以上、仕方ないのではないだろうかと思う。 そして、私が抱くある種の苛立ちとも言えるその感情は、 「そうではないワイン」 との数々の邂逅から来ている側面も強い。

梁 世柱
2023年11月24日


出会い <49> 時代の先を歩みすぎた偉大なワイン
Quinta da Pellada, Tounot 2011. 日本には数多くのワイン・インポーターが存在しているが、中には世界でもトップ・レベルの 先進性と審美眼 を兼ね備えた才能の持ち主を抱える会社がある。 そういったインポーターは、 世界の最先端と時差のないワイン を輸入し、日本のワイン市場が停滞しないための、重要な役割を果たしてきたとも言える。 しかし、彼らの先進性に、 市場やワインプロフェッショナルの理解が追いつかない ということもまた、 残念ながら幾度となく繰り返されてきた 。 その 最たる例 と言えるのは、 ドイツの辛口リースリング だろうか。 ドイツでは今から20年前にはすでに、世界のリースリング・マップを完全に更新してしまうレベルの、圧倒的な辛口リースリングが生産されていたが、長年の甘口路線が強烈に染み込んでしまった日本市場は、その先進性を頑なに拒絶し続けてきてしまった。 もちろん、そのムーヴメントの初期段階から、ドイツ産辛口リースリングのトップ・ワインを輸入していた国内インポーターはあったのだが、それらのワインが決して少なくな

梁 世柱
2023年11月19日
bottom of page