top of page
検索


出会い <96> 懐かしいワイナリーの衝撃的な新作
Bodegas Roda, Roda I Blanco 2021. ¥18,000 私がワインを学び始めた20数年前頃、スペインのとあるワインが、なかなかHIPな存在として注目されていた。 モダンリオハの雄と称されることも多い、 ロダ だ。 当時はロバート・パーカーJr.の影響力がまだまだ絶大だった頃というのもあり、「注目されている」ワインのほとんどが、まるで金太郎飴のように同じ顔をした、「違う国」のワインだった。 率直に言うと、ロダもまたその中の一つ、と言う印象だった。

梁 世柱
5 日前


SommeTimes’ Best Performance Award 2025
本年もまた、一年の締めくくりとなるBest Performance Awardの時がきた。 例年通り、選出基準は単純なコストパフォーマンスや、価格を度外視した品質といったものではなく、総合評価的に、最も強く印象に残ったワインを選出している。 本年は、クラシックとされるようなワイン(かなりの高額レンジも含む)と、日本ワインのテイスティング機会が例年よりも多い年となった。 同時に、クラシックワインとナチュラルワインも、その中間的なタイプも、満遍なくテイスティングを行ったという印象だ。 では、Awardの発表に移ろう。 Sparkling Wine部門 Ultramarine, Blanc de Noirs Heintz Vineyard “Late Disgorged” 2012.

梁 世柱
2025年12月28日


再会 <96> 歴史を創った中国ワイン
Ao Yun, Ao Yun 2019. ¥70,000前後 木を見て森を見ず 。 ワインを探究していると、往々にして陥りがちな 罠 である。 「あの国のワインは、イマイチ。」 ワイン識者らしき人が、迷いなくそう語る姿を目にしたことがある人は多いだろう。 しかし、 そのような見解は、ほとんど間違っている 。 低レベルなワインというものは、どの国にも等しく存在している。 ワイン大国と呼ばれるような、 フランス、イタリアといった国々も例外では無い。

梁 世柱
2025年12月23日


Not a wine review <6>
珍酒、奇酒の類は大好物だ。 日常的に、ワインという、ある意味では世界で最も「常識的」なアルコール飲料と関わっていると、その対極とすら言える存在に、どうも強く惹かれてしまう。 これもまた、ある種の「無いものねだり」なのだろう。 世界各国の珍しい酒と出会うたびに、心が躍る。 その酒が、どのような「変わった」味わいであったとしても、だ。 さて、今回出会った珍酒は、そのインパクトも強烈。 中国山東省青島で造られる、 即墨(ジーモー)老酒 である。

梁 世柱
2025年12月20日


Not a wine review <5>
日本人のキッチンに欠かせない調味料の一つである 「みりん」 。 甘味の調整にフォーカスが当たりがちだが、みりんはその 豊かなアミノ酸 によって 旨みとコク も加える。 そして、その甘味そのものも、調味料として重要な 他の役割 を担っている。

梁 世柱
2025年12月16日


出会い <95> 熟度の境界線
Vino della Gatta SAKAKI, 猫なで声 2024. ¥4,200 日本ワインに良く見受けられる問題として、葡萄の熟度不足が挙げられる。 この熟度とは、単純な糖度だけではなく、ポリフェノールなどの総合的な熟度であるため、その品種とその土地の相性も非常に重要となるのだ。 さて、ここで疑問を抱く人もいるかも知れない。 十分な熟度、と熟度が足りない、の境界線はどこにあるのだろうか、と。

梁 世柱
2025年12月9日


再会 <95> 究極的ブレンド・シャルドネ
Penfolds, Yattarna Chardonnay Bin 144 2021. ¥28,000前後 ワインを順当に学んでいくと、とある 一つの価値観 に支配されていくことが多い。 我々ワイン人が、 「テロワール」 と呼んでいるものだ。 その土地とその葡萄が出会ったからこそ生まれた個性。 テロワールという概念は、確かに我々に決して尽きない探究を与えてくれる。 テロワールの究極が「単一畑」という価値観が強いブルゴーニュを基準にすれば、より狭い範囲にその価値が高く宿ると考えることになるが、実際には、クラシックワインの世界ではもっと広範囲でテロワールの価値が認められている。

梁 世柱
2025年12月1日


出会い <94> 日本ワインの新たな方程式
The Rias Wine, Albarino 凪 2024. ¥3,200 日本における現在進行形のワイナリー設立ブームには、不安を覚える側面も多くあるが、希望の光も同時に多く見えている。 その最たる光とは、 フランス系国際品種偏重からの脱却 だ。 そもそも、ヨーロッパの中には、日本のワイン産地と気候条件がある程度近しい産地が、フランス以外にそれなりにある(むしろ、フランスの中にはあまり無い。)のだが、1980年代以降の日本ワインの発展は、実質的にフランス系品種に支配されてきた。 醸造用ブドウは、ちゃんと熟してこそ、真に意味性をもつ。 適していないテロワールで無理やり育てられ、結果としてしっかりと熟していない葡萄から造られた、密度が極端に低く薄いワインに、「日本らしさ」という言い訳を覆い被せるのは、実にナンセンスだと私は常々主張してきた。

梁 世柱
2025年11月25日


再会 <94> 見つからない伝説
Valentini, Montepulciano d’Abruzzo 2012. この世界に 「伝説」 とされるようなワインは、意外とたくさんある。 そして、その多くは、伝説と呼ばれる割には、簡単に探し出すことができる。 ただし、プレミア価格がついて二次市場で高額取引されるケースが残念ながら非常に多いため、実際の問題は、見つかるかどうかではなく、その対価を払えるかどうか、になるのだ。 もし誰かが私に、ロマネ・コンティを探して欲しいと頼んできた場合、ヴィンテージと価格にさえ縛りがなければ、数分もあれば探し出すことができるし、そもそも空港の免税店でも売っていたりする。 では、本当に見つからない伝説のワインとはどういうものなのだろうか。 真っ先に思い浮かぶのは、 ヴァレンティーニ だ。

梁 世柱
2025年11月18日


出会い <93> またまた出会った、最高のイタリアマイナー品種
Vignamato, Lacrima di Morro d’Alba 2022. 完全な専門分野として特化でもしない限り、イタリアのマイナーの地品種ワインは、とてもとても追いきれるものではない。 ブレンドまで含めると、そのヴァリエーションはまさに無数であり、そしてその事実は、我々を永遠に楽しませてくれるものでもある。 ネッビオーロ、サンジョヴェーゼ、アリアニコ、ネレッロ・マスカレーゼといった高名な葡萄への敬愛はなかなか捨てきれないので、ついついそういったワインに手を伸ばしがちだが、そこに「安心」はあっても、「驚き」はよっぽどのワインでも無い限り、そうそう訪れてはくれない。

梁 世柱
2025年11月10日


Wine Memo <36>
Astobiza, Arabako Txakolina “Pil Pil” 2024. ¥3,200

梁 世柱
2025年11月9日


再会 <93> デキャンタージュは万能薬ではない
Mathilde et Yves Gangloff, Côte Rôtie La Serène Noire 2010. 私は普段、無闇に デキャンタージュ することを、 非推奨 としている。 長い間瓶の中で 強い還元的状態 に置かれていたワインを、ウルトラデキャンターのような大きなデキャンタに移してしまうと、 急激な酸化によって、ある種の過呼吸的なパニック状態に陥る ことがある。 そのワインが秘めていたあらゆる繊細さが失われ、豊かな香りは消えさり、果実味は二次元的になる。 そのような最悪の結果を避けるために、デキャンタージュするかの判断は、極めて慎重に行うべきだと考えている。

梁 世柱
2025年11月3日


Wine Memo <35>
Arnoux-Lachaux, Vosne-Romanée 1er Cru Les Chaumes 2013. 先代のワイン、と聞くと、不思議とロマンの香りが漂ってくる。 ただしそのロマンは、往々にしてノスタルジアに似たものであり、ワインそのものの素晴らしさとは、少し評価の軸がずれたところにポイントが置かれていることも多くある。(その逆もまた然りだが。) 今回のWine Memoで取り上げたいのは、ブルゴーニュの「先代」ワイン。 ヴォーヌ=ロマネ村の古参ドメーヌとして知られた ロベール=アルヌー が、2008年に改称して誕生したのが、 アルヌー=ラショー だ。

梁 世柱
2025年10月31日
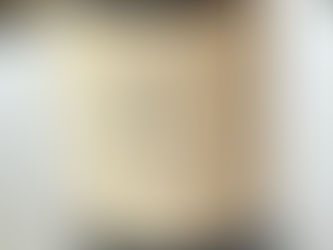

出会い <92> 中国ワインの巨星
Dan Sheng Di, Célèbre Red 2018. もう、6~7年前だろうか。私が初めて最高峰の 中国ワイン をテイスティングしたとき、少なからずショックを受けた。 今ではすっかり日本国内でも知名度が上がった Ao Yun は、日本で造られる同形品種のワインが(品質的に)到達することが極めて難しい領域にすでにいると、認めざるを得なかった。 もちろん、 品質だけがワインの全てではない。 その国、その産地だからこそ成し得た個性には、素晴らしい価値が宿る。 ただし、ワインをそのような価値観でもって受け止めることができる人は、国産バイアスが強烈にかかる初心者か、あらゆる国々のワインを飲み重ねてきた、歴戦の玄人くらいなものだ。

梁 世柱
2025年10月28日


再会 <92> 折衷派バローロの真髄
Aldo Conterno, Barolo Bussia Cicala 2017. ブルゴーニュの爆発的な高騰が終息しないなか、いわゆる「グラン・ヴァン(偉大なワイン)」を飲みたいと思った時、私の食指が バローロ・バルバレスコ へと動くことは格段に増えた。 かねてから、最上クラスのバローロ・バルバレスコは、ブルゴーニュに対しても全く見劣りしないと考えてきたが、これほど価格差が開いてしまうと、もはや私には偉大なブルゴーニュを自ら買って楽しむ「言い訳」を探すことが不可能となっている。 ブルゴーニュのグラン・クリュ一本に10万円を支払うなら、最高のバローロを4本飲みたい、というのが私の本音である。 さて、そんなランゲ地方の雄たちだが、現在は モダン派、古典派、折衷派の 3大スタイルが共存している。

梁 世柱
2025年10月21日


出会い <91> 北海道で華開くドイツ系品種
山田堂, Yoichi Blanc 2024. ¥2,800 寒冷地である 北海道 が、 1970年代 から ドイツ・オーストリア系品種 に目をつけたのは、英断だった。 1976年のパリスの審判 をきっかけに、世界各地で爆発的に フランス系国際品種 が広まることになったのだが、その大波が本格化する前に、 ミュラー=トゥルガウ、ケルナー、バッカス、ツヴァイゲルト(レーベ) などの葡萄が北海道に導入されたのは、運命のいたずら、とすら言えるのかも知れない。 パリスの審判から、ロバート・パーカーJrの台頭という一連の流れの中で、2010年代に入るまでは、パワー型ワインの全盛期となったため、繊細な北海道のドイツ・オーストリア系ワインがセールスに苦しんだことは想像に難くないが、耐え忍んだだけの価値はあったと、私は思う。

梁 世柱
2025年10月14日


再会 <91> 最強シャンパーニュの大当たりボトル
Alain Robert, Le Mesnil Réserve 1988. (Magnum) 私はシャンパーニュが大好きだ。シャンパーニュの無い人生など、もはや考えられない程に。 確かに、世界的な気候変動や技術向上によって、一般的なレベルのシャンパーニュと比べた場合、遜色ないと言える品質のスパークリングワインは、世界各地で劇的に増えた。 しかし、頂点と呼べる品質領域においては、 シャンパーニュが王者のまま 、というのが私の見解である。 今回は、そんな頂点シャンパーニュの中でも、特に私が執着しているワインとの再会。 アラン・ロベール 。

梁 世柱
2025年9月30日


出会い <90> ポルトガル=オレンジワインのホットゾーン
Espera, Espera Curtimenta 2022. ¥3,900 オレンジワインとは、つくづく興味の尽きないジャンルだと思う。 その理由は、 「常識の破壊」 にある。 シャルドネ、ソーヴィニヨン・ブラン、リースリング。我々が白ワインとして慣れ親しんだ葡萄が、オレンジワインとなった途端に、 全く未知の姿 を見せる。

梁 世柱
2025年9月25日


再会 <90> 頂点であるということ
Domaine de la Romanée-Conti, Grands Échézeaux 2015. ワインには、 ヒエラルキー というものが存在する。 嗜好品だから個人の好みなのに、飲んだら消えてしまうようなものなのに。 色々と言いたいことが出てくる気持ちは分かるが、こればかりはどうしようもない。 音楽で例えてみよう。 中学生の素人が宅録した音源には、そこにしか無い素朴で原始的な魅力が確かにあると思うが、一流のプロが経験と技術とお金を注ぎこんで作り上げた音楽との「品質」的差異は、否定のしようがない。

梁 世柱
2025年9月17日


出会い <89> 無添加甲州の可能性
Kitani Wine, 甲州 キュヴェ・タカシ 2023. ¥2,800 日本が誇る地品種(厳密に言うと中国からの渡来品種ではあるが)である 甲州 は、まだまだ完成系と言える姿を示していないと、私は考えている。 中央葡萄酒(Grace)の三澤甲州(旧キュヴェ三澤 明野甲州)のように、逸脱した領域に踏み込み始めたワインも登場してきてはいるが、それでもまだ、甲州という葡萄はあらゆる進化の可能性を残しているのではないだろうか。 映画「ウスケボーイズ」のモデルとなった人物としても知られるシャトー・メルシャン元工場長の浅井昭吾(ペンネーム:麻井宇介)氏が、フランス・ロワール地方のミュスカデから着想を得た、甲州に シュール・リー製法 を用いるという手法を、1985年に他の日本ワイナリーへ公開して以降、そのスタイルは確かに現代に至るまで甲州ワインの地盤を固めているが、まだまだ見えていない「その先」があるはずなのだ。

梁 世柱
2025年9月10日
bottom of page