top of page
検索
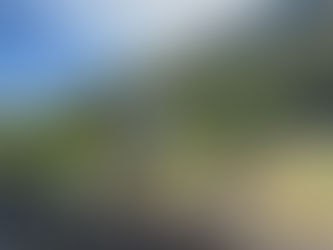

ワインで巡る火山の島々
シチリア、エオリエ諸島 イタリアには 無数の固有品種 や、その土地に根付いた ユニークなスタイルのワイン が多く存在するが、なかでも個性が際立つ 火山島のワイン を紹介しよう。2022年9月、私はシチリア島の北方、ティレニア海に浮かぶ美しいエオリエ諸島を訪問する機会に恵まれた。もちろん、ワイン産地視察という目的ではあったが、海、島、火山というワインに紐付くテロワールを構成する「自然」に、純粋に心踊る旅となった。 2000年にユネスコ世界自然遺産に登録されているエオリエ諸島の主要な7つの島は、次の通り。 ● リパリ島 ● サリーナ島 ● ヴルカーノ島 ● ストロンボリ島 ● パナレア島 ● フィリクーディ島 ● アリクーディ島 シチリアのエトナ山はヨーロッパ最大級の活火山として有名だが、エオリエ諸島も海底火山の活動によって形成された島々で、ストロンボリ島では現在も活発な火山活動がみられる。今回は、ワイン造りが行われている主要3島を巡った。 マルヴァジア・デッレ・リパリ Malva

高橋 佳子
2023年2月21日


別色の未来 <南アフリカ特集:最終章>
南アフリカを訪れる前は、まだ疑問が残っていた。 瞬く間に成長してきた南アフリカは、すでにアメリカ合衆国、オーストラリア、ニュージーランド、チリ、アルゼンチンといったニューワールド先進国と、肩を並べる存在になっているのか。その立ち位置に相応しいワイン産出国としての総合力をすでに得ているのか、と。 もちろん、サスティナビリティへの取り組みや、日本に輸入されている様々なワインの実力は知っていたが、現地の様子を自身の目で見て、造り手と直接会話し、葡萄畑を歩き回り、最もフラットな現地リリースのコンディションでテイスティングしない限り、私はその産地の実力を、外部の情報とワインだけを頼りに、盲目的に信じたりはしない。いや、そんなことができると真に思うほど、自身を過大評価してなどいないのだ。 私のようなものが言うのもなんだが、活字は平気で嘘をつく。 だからこそ、真実は必ず、自ら確かめる必要がある。 過去数年間、少なからず南アフリカのワインに、遠く離れた日本の地で心躍らされてきた身としては、ついに真実を見るであろうことに不安がなかったわけではない。 だが、幸いなこ

梁 世柱
2023年1月28日


未来からの預かりもの <南アフリカ特集:第4章>
南アフリカ滞在中、一人の見知らぬ若い女性から、苦言を受けた。

梁 世柱
2023年1月15日


共に歩み、共に得る <南アフリカ特集:第3.5章>
一人で叶えられることは、とても限られている。 人がどれだけ孤独という人生のスパイスを好んだとしても、真の孤独が奇跡的な確率でのみ生みだすことができるのは、永遠に語り継がれる様な至極の芸術作品しか無い。 人はその真理を理解しているからこそ、手を取り合う。 そして、共に歩み、共に得ようとする。 南アフリカのワインが、驚異的なスピードで世界のトップ層へと躍進した理由は、恵まれたテロワールの存在だけでは無い。 そこには人がいて、人と人の繋がりがあった。 成功も失敗も共有し、共に学び、鼓舞しあい、切磋琢磨する。 南アフリカで見た無数の「繋がり」こそが、躍動の原動力なのだ。 生産者団体 ワインの世界には、様々な生産者団体がある。中には、 ドイツのV.D.P のように、国のワイン法すら変えてしまうほどの絶大な影響力をもつ団体や、 Renaissance des Appellations のように、国境を越えたビオディナミ生産者の団体もあるし、 カリフォルニアのI.P.O.B のように、志半ばで空中分解してしまった団体もある。 規模の大小や性質の違いはあれども、

梁 世柱
2022年12月22日


古きものが、未来を照らす <南アフリカ特集:第3.0章>
私の祖母は、他国間の戦場と化し、唐突に、強引に分断された国から、命懸けで脱出した。そして、祖母が負ったリスクのずっと先に、私という存在がいる。 祖母の歩んだ激動の人生は、そのまま私の人生観、そして価値観の土台となった。 今は過去の先にあり、未来は過去と今の先にある。 その繋がりこそが、輝きをもたらす。 南アフリカで、私が亡くなった祖母のことを思い出したのは、決して偶然ではない。 あの地にはあった。私は確かに、この目で見た。 古きものが、過去と今を繋ぎ、未来を照らす姿を。 Old Vine Project 南アフリカワイン産業の極めて重要な取り組みとして、その名を挙げない訳にはいかないのが、 Old Vine Project だ。 南アフリカでも最も尊敬を集める、葡萄栽培のトップ・エキスパートである ローサ・クルーガー が、2002年に複数の栽培家と共に南アフリカ全土に点在する古樹の調査を開始したのが、このプロジェクトの始まり。 2006年に イーベン・サディ がOld Vine Seriesを初リリースしたのをきっかけに、2010年ごろには...

梁 世柱
2022年12月15日


呼応するニュー・ワールド <南アフリカ特集:第2章>
集合意識 というのは、非常に興味深い概念だ。直接的なコミュニケーションをとっているわけでも無いのに、何かしらのミディアムを通じて、度々 全世界を包み込むようなイデオロギーの変化 が生じる。 人種差別、性差別、人権侵害、軍事的侵略行為への反対といった人そのものの在り方に関わるもの、オーガニックやサスティナビリティの推進といった地球と人間の双方に関わるもの、食のライト化といった人の趣味嗜好に関わるもの。近代から現代にかけて起こった集合意識によるイデオロギーの変化だけでも、まだまだ長いリストができるだろう。 そして、 変化と自戒は往々にして表裏一体 である。 様々な差別を繰り返してきたことに対する自戒、人類史のほとんどを戦争と侵略で埋め尽くしてきたことへの自戒、環境破壊を積み重ね深刻な気候変動を招いたことに対する自戒、生活習慣病の爆発的増加への自戒。 先述した全ての変化に、その根源となった自戒が存在し、折り重なった自戒は、やがて集合意識となって、全世界規模の改善を促し始める。 それらに比べるとずっと規模は小さいが、ワインの世界でも、同様の集合意識による

梁 世柱
2022年11月30日


Black and White <南アフリカ特集:序章>
30時間の長旅を終え、私は地球の真裏へと降り立った。ため息のような深い呼吸をすると、乾燥した心地良い空気に、知らない香りが混ざり込む。深緑色の野草。紅色の花。未知の風景に沸き立つ感情が、体の節々を駆け回る鈍い痛みを優しく包み込んだのも束の間、だんだんと私の心は灰色に濁り始め...

梁 世柱
2022年11月12日


再発見された銘醸地 <ギリシャ・ナウサ特集:導出編>
私は感覚的印象と論理的考察が入り混じって生じた 確かな疑念 を抱えて、ナウサの地に降り立った。 感覚的印象は、私がこれまで ナウサに素晴らしい可能性を感じつつも、実体験として心を激しく揺さぶるようなワインにはほとんど出会ってこなかった ことに起因する。 論理的考察は、 二つの疑問点 によって疑念を強める要因となってきた。 一つは、 「ナウサがもしギリシャの産地で無ければ」 、と言う疑問だ。 この場に私自身が嫌悪するブランド至上主義をもちこむ気は毛頭無い が、例えばナウサがもし、地品種ワインの世界的リーダーであるイタリアの産地だったとしたら、これほどの注目を集め得たのだろうか、と言う疑問がどうしても残っていた。別格のネッビオーロは横に置いておいたとしても、クスィノマヴロが果たしてサンジョヴェーゼ、アリアニコ、ネレッロ・マスカレーゼ、サグランティーノといった葡萄と横並びに語れるほどの資質をもっているのか。遠く離れた日本からでは、確信に至ることはできていなかった。ギリシャの偉大な赤ワインの産地はナウサしかない(事実とは異なるが)というイメージが先行した

梁 世柱
2022年10月31日


復活の起点 <ギリシャ・ナウサ特集:導入編>
アラビア半島を飛び立った私は、砂海に浮かぶ星々のように小さな ギザのピラミッド群 を眼下に収め、 荘厳なアクロポリス と 静 謐 なる霊峰オリンポス を横切りながら進んだ。 古代の神秘を巡るその道のりはまるで、けたたましいエンジン音を撒き散らす無機質な巨塊ではなく、優美に羽ばたく大鷲の背に乗っているかのように軽やかで、ずいぶんあっさりと、私は幻想の世界に没入していった。 そして、アレクサンドロス大王が治めた地に降り立った私は、強引に現実世界へと引き戻された。私が向かった先は、皆が思い浮かべるような、碧い海に囲まれた美しい島々ではない。そこは、激しく隆起する大地と混じり合うように拓かれた小村が点在する山の国、 マケドニア 。ギリシャでありギリシャではない、歴史的、文化的にも極めて独自性が強いこの地には、世界中が注目する一つの小産地、 ナウサ がある。 東から西へ 〜古代ワイン文明の中心地ギリシャ〜 ギリシャにおける最も原始的なワイン造りの痕跡は、 少なくとも紀元前4,000年、おそらくは4,500年ごろまで遡れる と考えられている。どちらにしても、

梁 世柱
2022年10月15日


ペロポネソスのダイナミズム <西ギリシャ特集>
ギリシャワインというと、近年、日本でもその存在感がじわりと出てきているのではないだろうか。今から10年ほど前、 サントリーニ島のアシリティコAssyrtiko が国際的に評価されたと同時に、その強烈な個性を印象付けた。 エーゲ海の島、海と空のブルーのコントラストに、くっきりと浮かび上がる真っ白い建物、強風からブドウを守るためにバスケット状に仕立てられたユニークなブドウ畑の風景、火山由来の極端に痩せた土地のテロワールが産み出す強靭な酸味と塩味を帯びた凝縮した果実味。 これらの要素は、視覚的効果を伴いながら、見知らぬ土地の固有品種から造られるワインにとって、少なくとも専門家の注目を集めるのに余りあるインパクトと付加価値を与えた。 それに続いたのが、対照的な 山のワイン、ナウサのクシノマヴロXinomavro だろうか。北イタリアのネッビオーロに特徴が似ているという点が、アピールポイントとなった。(ナウサのレポートは10月にアップデート予定) 世界的ワイン教育プログラムWSET®のLevel 3の教本では、これらに ネメアのアギオルギティコAgiorg

高橋 佳子
2022年9月12日


考え抜くものたち <長野・千曲川ワインヴァレー特集 第2章>
日本ワインに明るい未来はあるのか。 その問いへの答えを探るには、何をもって「明るい未来」と考えるかを明確にしておく必要がある。 日本ワインが、現在の在り方の延長線上、つまり 日本国内消費量が極端に多い状況で発展していくだけ なのであれば、 その未来は明るい と言えるのかもしれない。 地産地消の流れがますます加速し、まだ産声を上げたばかりの産地にも第二、第三世代が現れれば、文化が徐々に形成され、地域に根付いていく。 日本人らしい丁寧な「モノづくり」を続けている限りは、安泰と言っても基本的には差し支えないだろう。 一方で、 世界の中での立ち位置を基準に考えた場合 、現状のまま日本ワインが「明るい未来」を迎える可能性は、 絶望的に低い 。 そしてその理由は、 ワインそのものの品質や個性では決してない 。 今、突破不可能とすら思えるような サスティナビリティという巨大な壁 が、日本ワイン産業の目前にまで差し迫っていることに気付いている消費者やプロフェッショナルは、非常に少ない。 そう、現在世界中のワイン産地が最重要視していることが、何よりも日本では難しい

梁 世柱
2022年8月31日


繋ぐものたち <長野・千曲川ワインヴァレー特集 第1.5章>
「ここがワイン産地として成立しているのか、まだ良く分からない。」 ドメーヌ・ナカジマの 中島豊 さんが語った言葉は、この旅の中でも特に印象に残るものの一つだ。 現在千曲川ワインヴァレーには、 30軒の(醸造所付き)ワイナリー がある。 この数を少ないと思うか、意外と多いと思うのかは人それぞれだが、少なくとも「ワイン産地」と呼ぶには、世界各地の実情を鑑みる限り、 数だけなら十分 と言えるだろう。 一つの原産地呼称制度内に、一つのワイナリーしか存在していないケースは多々あるし、20軒程度でも原産地呼称を得ている広い産地も少なからずある。 では、それらの産地と千曲川ワインヴァレーを 隔てるもの があるとしたら、それはなんなのだろうか。 千曲川ワインヴァレーを総合的に見ると、まだワイン産地とは言い切れない理由があるとしたら、なんなのだろうか。 それは、 歴史と文化 だ。 歴史はそのまま年数でもあるため、この点はもうただただ待つしかない。 しかし、文化は違う。 文化とは人が作り上げるものだ 。そして、文化の構築は より広範囲で行えば、短時間でも可能 だ。.

梁 世柱
2022年8月23日


突き進むものたち <長野・千曲川ワインヴァレー特集 第1章>
梁世柱は日本ワインに冷たい。 散々言われてきたことだ。 確かに私自身もそれを否定できないという自覚をはっきりともっているが、そこには 明確な理由 が常にあったのもまた事実だ。 日本で造られたワインが、海外の(特にヨーロッパの)ワインに対する オマージュやイミテーション である限り、私はその元となったワインと 同じ評価基準で日本ワインを評価するしか選択肢が無くなる 。 その評価基準とは、ヨーロッパの 古典的価値観に基づいた品質評価 、そして その品質とワインに付けられた価格のバランス だ。 そもそも日本のテロワールに適合してるとは、ヨーロッパの基準で見れば到底言い難い外来種の葡萄を、極限の献身と、深い知恵でもって育てても、適地適品種という残酷なほど強大な壁にぶつかることは避けられない。当然、そこまで辿り着くための献身や知恵にも、多大なコストがかかる。 その結果、同程度、もしくはそれ以上の品質評価ができる海外産のワインが、日本ワインの半額以下で、「輸入品」として手に入ってしまう、という絶望的な状況から抜け出せくなってしまう。 私が多くの日本ワインに対

梁 世柱
2022年8月14日


オーストリアのグリーン・ハート シュタイヤーマルクを歩く <オーストリア特集:後編>
オーストリア南部の シュタイヤーマルク は、まだ「知られざる産地」と表現した方がいいだろうか。この産地の特徴は、「ナチュラル」「ミネラリー」そして「フルーティ」な、世界に類を見ないスタイルのソーヴィニヨン・ブランだ。5月に当産地協会のツアーに参加した内容をここではレポートしたい。 セップ・ムスター、アンドレアス・ツェッペ、ヴェルリッチ、シュトロマイヤー 。 シュタイヤーマルクは、一部で熱狂的なファンを持つ ナチュラルワインの生産者 たちが本拠としている産地だ。 しかし、ナチュラルワインの聖地だ、という理解で終わっていないか? シュタイヤーマルクとはそもそもどのような産地なのか 、考えてみたことはあるだろうか? オーストリアを代表する品種、 グリューナー・フェルトリーナーがほぼ存在しない産地 、シュタイヤーマルク。今回当地のワイン協会主催のツアーに参加し、その独自性と面白さに改めて驚かされることとなった。オーストリア編後半の本稿では、シュタイヤーマルクという産地の特徴に改めて目を向けてみたい。ナチュラルワインのイメージに覆い隠された、その特異性や多

別府 岳則
2022年7月27日


前進するオーストリアワイン <オーストリア特集:前編>
最良のオーストリアワインとは何か? という問いには、様々な答えがあるだろう。 とはいえ少なくとも、素晴らしいテロワールから生まれるワインだ、ということについてはどなたも同意いただけるのではないか。 ではオーストリアの優れたテロワールとはどこか? そこにはどのような特徴があるのだろうか? 今後、例えばハイリゲンシュタインの名前はさらに重要性を増すだろう。 オーストリアのほぼ全ての畑をデジタルデータにするという意欲的なプロジェクト が指し示す先は、更なるそれぞれの畑への理解と、優れたテロワールへの希求である。 VieVinum ウィーンで2年に一度開催される「 VieVinum 」は、 世界で最も美しいワインフェア ともいわれる。それは会場となる ホーフブルグ宮殿 の美しさによるものか、それとも出展者から供されるオーストリアワインによるものだろうか。 Covid-19のため前回はキャンセルとなり、4年ぶりの開催となった今年は、待ちに待った生産者と世界中から集まったプロフェッショナルの再開を喜ぶ空気が会場に溢れていた。 400社以上が出展する...

別府 岳則
2022年7月12日


自然農法の真理 <後編>
私は、昨年の春からこの冬の間中ずっと思い悩んでいたことがあった。 「なぜ人間は、野に舞う蝶や、空飛ぶ鳥のように自由に生きることができないのか…。」 その悩みに答えを示してくれたのが、 福岡正信氏 だ。 自然農法の大家、福岡氏の遺した数々の言葉。 それらは、表面的には 非常に宗教色が強く思えるかも知れないが、その本質は大きく異なる 。 氏の鋭く、時に断定的な言葉使いを、断片として切り取ってしまうと、真意を読み誤ることもあるだろう。 よって、以降の内容を、 宗教的という目線から考えないことを、強く推奨する 。 福岡氏の言葉も、 本意としては様々な宗教を否定するものでは決してなく、氏の言葉をもとに書かれたこの記事もまた、宗教を否定する類のものでは一切ない 。 真理 福岡氏の 「無の哲学」 では、仏教における 「空」の思想 をもとにした、氏の思想が語られている。 福岡氏は著書で何度も 「真理は一つだ」(絶対的真理) と言っているのだ。 その真理とは。 「 絶対的真理 は、無力どころか、架空の概念を一時的に満足せしめるに役立つのみの科学的真理よりも、より強

ソン ユガン
2022年6月28日


自然農法の真理 <前編>
福岡正信氏とは?と聞かれて一言で答えることができる人がどれ程いるだろうか。 自然農法の人、粘土団子の人、わら一本の革命の人。 世界のワインに通じる方なら、氏について知っているかもしれない。 海外に通じるワインプロフェッショナルなら、氏について聞かれたことがあるかもしれない。 実は、新型コロナ禍で世界の価値観に変化の兆しが見えている。 今、世界的に、東洋的思想が再評価されてきているのだ。 本特集では、福岡正信氏とは一体だれなのかを、丁寧に紐解いていく。 自然農法の本質、その実践に至った経緯、そして氏の哲学。 その思想は農業にとどまらず、人間性、神性、生き方へと繋がり、この現代社会を導く灯火ともなる。 そしてそれは、日本の農業、ブドウ栽培とも関わりがある。 福岡正信氏とは? 私はこう答える。 「キリストやガンジーのように真理を振りかざし、仏のように慈悲をもって無に還ろうと絶叫した百姓であり、哲学者であり、ある種の神性を得た存在。」 と。 本特集は、なるべく福岡正信氏自身が著書内で語っている内容をそのまま使用するよう努めているが、私の個人的な見解も多分

ソン ユガン
2022年6月15日


高みへと <ロワール渓谷特集:最終章>
ロワール渓谷のソーヴィニヨン・ブランには、どうも複雑な思いが拭いきれずにいた。 セントラル地区 は、この品種の 世界的聖地 とされてきたが、特に日本においてはあまり話題に上がることもないし、レストランやショップでも、それほど見かけるわけでもない。同じくフランス国内にある、その他品種の「聖地」と比べれば、その歴然とした格差に正直驚きも隠せない。一般的なワインショップなら、ブルゴーニュの品揃えはサンセールの10倍を遥かに凌駕するだろう。 価格だけを見れば、もう一つのソーヴィニヨン・ブラン伝統産地であるボルドーの後塵を拝したままどころか、その差はますます広がる一方だ。 ふと、頭によぎる。サンセールやプイィ=フュメは、名前だけの聖地なのかと。フランスの産地である、という理由だけで、聖地に押し上げられた存在なのかと。 オリジンとパーソナリティ ロワール渓谷のセントラル地区( 以降、ロワール・セントラルと表記 )がソーヴィニヨン・ブランの聖地と見なされてきた確実な理由の一つとして、その 歴史 を挙げることができる。現時点で判明している限り、...

梁 世柱
2022年5月31日


アイデンティティの行方 <ロワール渓谷特集:第三章 >
悲壮感漂うワイン。 カベルネ・フランから生み出される、ロワール渓谷を代表する数々の素晴らしい赤ワインを一言で表すとそうなる。 華やいだスミレの香りと、力強い大地のトーンが交差し、ワイルドとエレガンスを行き来しながら、メンソールのような心地よい余韻へと誘われる。最高のテロワールと、最適な品種と、奥深い伝統が織り成していた確かな 様式美 は、その多くが すでに過去 のものだ。 かつて、葡萄品種とテロワールの統合的特性である「青い」風味を、絶対的な悪と見なした評論家がいた。彼はそういったワインに平然と60~70点代という低スコアを叩きつけて、ボルドーだけでなく、ロワールのカベルネ・フランという伝統をも、根底から否定した。そこまでなら、ただの一意見に過ぎなかったはずだが、真の問題は別のところにあった。自らの感性を信じず、他者の、しかもたった一人の他者の評価を絶対として信じた主体性なき群衆が、意気揚々と非難の声をあげて同調してしまったのだ。まるで、突然手のひらを返すかのように。 世紀の変わり目を迎える頃には、ロワール渓谷の偉大な赤ワインは、すっかり様変わり

梁 世柱
2022年5月21日


伝統と変化 <ロワール渓谷特集:第二章 後編>
少し古いワイン教本を読むと、ロワール渓谷のシュナン・ブランの特徴として、「 濡れた犬 」、「濡れた藁」、「 濡れた羊毛 」といった表現が頻出する。確かにかつて、この地のシュナン・ブランには「濡れた」何かの印象が強く残るものが多かった。その主たる要因として、 葡萄の熟度の低さ が挙げられることは多いが、 温暖化や収穫時期の見直し (より遅摘みへと変化)が進んだ現在は、 その特徴はほぼ完全に消失 したと言える。 素材の状態が変わると、当然のようにレシピにも変化が起こる 。まず、 熟度の高まり と、それに並行して広まった オーガニック栽培への転換 は、 野生酵母での発酵と亜硫酸添加量の大幅な低下 と言う一つの大きな流れを生み出した。野生酵母がよりテロワールを正確に表現するかどうかという議論はここではしないが、亜硫酸添加量の低下は、強烈な酸とミネラルで、とにかく「固い」印象の強かったシュナン・ブランに、 確かな柔らかさ をもたらした。 もう一つの大きな変化は、 意外なところ から生まれた。 空調の導入 だ。通年で低温を保てる地下カーヴがほとんどないロワー

梁 世柱
2022年5月10日
bottom of page