top of page
検索


SommeTimes’ Académie <102>(イタリア・トスカーナ州: Part.3)
一歩進んだ基礎の学び、をテーマとするのが SommeTimes’ Acad é mie シリーズ。 初心者から中級者までを対象 としています。 今回はイタリア・トスカーナ州について学んでいきます。 イタリアを代表する銘醸地の一つであるトスカーナ州は、イタリアで最も偉大な黒葡萄の一つであるサンジョヴェーゼを主力にしつつ、国際品種やその他の地品種でも多大なる成功を収めてきました。 また、オーガニック/サスティナブルへの取り組みも、イタリアで先陣を切っており、イタリアワイン産業のリーダーとして、力強く歩んでいます。 トスカーナ州編第3回では、トスカーナ州の中でも三大サンジョヴェーゼ銘醸地の一つとされる、 Brunello di Montalcino D.O.C.G. に関して学んで行きます。

梁 世柱
2025年8月1日


出会い <81> 新世代のブラウフレンキッシュ
Gober&Freinbichler, Blaufränkisch Horitshon 2020. 私がオーストリアワインを学び始めた約20年前、彼の国を代表する偉大な黒葡萄である ブラウフレンキッシュ は、どのテキストをみても 「エレガント」 な味わいであると表現されていた。 違和感 があった。 興味をもって、色々とテイスティングしてみていたのだが、どのワインもどちらかというとカベルネ・ソーヴィニヨン的な性質で、エレガントという表現に結びつけられるピノ・ノワール感を、ほとんど感じることができなかった。

梁 世柱
2025年5月5日


出会い <71> もう一つの大銘醸地
Prieler, Ried Steinweingarten 2022. ピノ・ブラン は 「偉大なワイン」 となれるのだろうか。 おそらく、100人のワイン好きに訊ねても、Yesと答える人は1人いるかいないか、だろう。 それもそのはず。 そもそも、 ピノ・ファミリー の中では圧倒的にピノ・ノワールの知名度と人気が高く、ピノ・ブランは実質的に、ピノ・ノワールの劣化版亜種のような扱いを受けている。 さらに、 ピノ・ブランが一般的に最も良く知られている産地 は、 フランスのアルザス地方 だと思うが、そのアルザスにおいても、ピノ・ブランは主役の座からは程遠く、高貴品種には同じピノ・ファミリーであるピノ・グリが名を連ねている。

梁 世柱
2024年11月4日
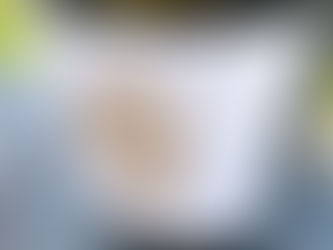

出会い <70> ノーマークだった、極上シャルドネ
Markus Altenburger, Ried Jungenberg Chardonnay 2022. 完全にノーマークだった産地と葡萄品種の組み合わせに、心底驚かされることが時々ある。 そのような発見は、ワインを広く深く探究していくことの、 最大の醍醐味 の一つだ。 今回の「出会い」ワインは、 オーストリア・ブルゲンラント州 で、ブラウフレンキッシュやツヴァイゲルトを集中的にテイスティングする最中で出会った、 驚異的なシャルドネ 。 このシャルドネが育まれたのは、 Leithaberg DAC 内の小地区である Jois(ヨイス) 。ノイジードル湖の北端から北、ライタ山脈の麓に広がる、 Leithaberg最東端のエリア だ。

梁 世柱
2024年10月20日


黒の楽園 <オーストリア・ブルゲンラント特集:前編>
ワイン産出国としてのオーストリアを象徴しているのは、グリューナー=ヴェルトリーナーとリースリングをダブル主役とする、圧倒的な品質領域にある白ワインの数々。 そこに異論があるわけではないが、 相対的に赤ワインが過小評価されている 点に関しては、納得がいかない。 ブラウフレンキッシュ 、 サンクト・ラウレント 、そして ツヴァイゲルト 。 オーストリア三大黒葡萄の全て、とまでは言わないが、少なくとも 最上の例 に関しては、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガルなどの象徴的な黒葡萄と比べても、 遜色する点など全く見当たらない からだ。 つまり、それらの主産地であるブルゲンラント州は、ボルドー、ブルゴーニュ、ローヌ、ピエモンテ、トスカーナ、リオハ、リベラ・デル・デュエロ、ドウロなどと、 本来なら並び称されるべき産地 であると、私個人の意見をここに強く記しておこう。 私自身、ブルゲンラント州の赤ワインとは、随分と長い間向き合ってきた。 調和に満ちたブラウフレンキッシュ、エネルギッシュなサンクト・ラウレント、変幻自在なツヴァイゲルト 。 魅力の在りどころは

梁 世柱
2024年10月17日


問われる真価 <オーストリア・カンプタール特集>
オーストリアを象徴する葡萄品種といえば、グリューナー=ヴェルトリーナーとリースリング。 ブラウフレンキッシュやツヴァイゲルトなど、同国には偉大な黒葡萄も存在しているが、一般的なレベルでのオーストリアワインへの理解という意味においては、間違いなく白葡萄の両巨頭に軍牌が上がる。 そして、その白葡萄を象徴する産地は、 Wachau である。 むしろ、Wachau一択、としても過言では無いほど、彼の地の総合力は他を圧倒してきたと考えられている。 だが果たして、本当にそうなのだろうか。 本当に、Wachauが唯一無二の絶対王者なのだろうか。 それを確かめるには、もう一つの産地を深く理解する必要がある。 Wachau最大のライバル候補、 Kamptal だ。 Kamptal Wachauの東端からKremstalを挟んで、 ランゲンロイス の街を中心に、ドナウ川に合流する直前の カンプ川流域 に広がっているのがKamptal。 葡萄畑は カンプ川北部(左岸)の南向き急斜面 (一部はテラス状)と、川により近いなだらかな 平地エリア に集中している。また、Wac

梁 世柱
2024年10月4日


その畑には、奇跡が宿る <オーストリア・ヴァッハウ特集後編>
格付け は、 旧時代の遺物 なのかも知れない。 多様性の尊重が声高に叫ばれるようになってから、その思いが私の脳裏から離れなくなった。 確かに、時代は順位を、優劣を、忌避している。 他者よりも優れていることが絶対的な価値では無い。 ありのままの個性を磨けば良い。 そもそも、その順位や優劣は、誰がどの価値観に基づいて決めたのか。 まるで 呪い のように繰り返されるそれらの言葉に抗うのは、実に骨が折れることだ。 実際、 テロワールが導き出す優劣は、この上なく残酷なもの である。 複雑性と調和が格を決める 。そこに 個性が認められる余地 はあったとしても、最終的な価値判断は、厳格なリアルとして佇む。 生産者の常軌を逸した努力によって、ワンランク上のテロワールへと到達できることは稀にあったとしても、最低ランクの葡萄畑が、特級畑クラスへと昇華するような奇跡は起こらない。 やはり、前時代的ではあるのだろう。 だが、私は頑固者だ。 勝ち負けの無くなったスポーツになど、全く興味はない。 美味い料理は美味いし、そうではない料理の中には、不味いものもある。...

梁 世柱
2024年9月20日


特異点の完全性 <オーストリア・ヴァッハウ特集前編>
オーストリアで、 総合的に最も優れた産地 はどこか。 いくら捻くれた性格の私でも、その問いに対しては、一瞬のためらいもなく Wachau(ヴァッハウ) と答える。 テロワールの質と好適品種として根付いた葡萄の極まった相性、品質の最高地点と最低地点の平均値、逸脱して優れた造り手の数、オーガニック比率の高さ。 どれをとっても超一級 であり、白ワイン以外ほとんど造られていない、ということが弱点にすらならないほど、 ヴァッハウの特異性は限界突破 している。 それでも私は、 日常的にヴァッハウを飲むことはほとんどない 。 「不完全なものにこそ、人間性を感じる。」 という、私の「人」としての在り方が、ヴァッハウの 完全性 とは本質的に相容れないからだ。 ヴァッハウを飲む、という行為は、私にとっては美術館で人類史に残るほど優れたアートを鑑賞するに等しく、実に 非日常的な行動 である。 同じような理由が、ブルゴーニュ、ボルドー、シャンパーニュ、モーゼル、ラインガウなどにも当てはまるように思われるかも知れないが、そうではない。

梁 世柱
2024年8月30日


出会い <66> 聖地のニュースター
Daniel Jaunegg, Sauvignon Blanc “Muri” 2021. 近年の日本における学校教育の実態を聞いて、私は開いた口が塞がらなくなった。 どうやら子供達に、 徹底的に「競争」を避けさせている 学校が数多くあるらしいのだ。 勝者と敗者を同時に生む競争の弊害 に関しては、理解できる部分ももちろんある。しかし、運動会の徒競走で順位を決めないなどは、正直あまりにも極端に思えてならない。 切磋琢磨 、という言葉はもはや死語なのだろうか。 そういう私自身も、旧時代の遺物として揶揄されることになるのかも知れないが、私は 純然たる事実 をここに書き記そう。 今の私は、絶え間ない競争の果てに在る 、と。

梁 世柱
2024年8月25日


PIWI品種とナチュラルワイン <オーストリア・シュタイヤーマルク特集:Part.3>
気候変動とナチュラルワインは、すこぶる相性が悪い。 低介入醸造を可能とする葡萄の必須条件 はいくつかあるが、その最たるものは、 低いpH値 (単純化すると、高い酸度)と、 高いポリフェノール類の熟度 だ。 気候変動の一部である 温暖化 は、糖度の上昇を大幅に加速させるため、低介入醸造を 重要視する 造り手たちは、 アルコール濃度の抑制と低pH値のために、早摘みを余儀なくされる 。 しかし、 過度の早摘みは未熟なポリフェノールともダイレクトに繋がる ため、 結局問題が起こる 。 この 堂々巡り を回避するために、栽培品種が今の気候に適しているかどうかも含めた 畑仕事の根本的な見直し や、糖度上昇の加速によって 劇的に狭まった「適熟」のスイートスポットを、決して逃さないように収穫 することが、かつてないほど重要になっているが、当然それも、簡単なことではない。 特に収穫タイミングに関しては、超速で飛ぶジェット機を、連写機能を一切使わずに写真に収めるようなものだ。 栽培に関しては他にも、オーガニックという大きなカテゴリーの生産者に

梁 世柱
2024年8月16日


レジェンドの息子 <Elias Musterの挑戦>
ワイナリーの継承 というのはとても難しい。 そもそも子供世代が 大変な農作業 を伴うワイナリーを引き継ぎたいとも限らないし、親が造っていたワインの 品質を維持 できるとも限らない。 ワイン造りに 「人」が深く関わってくる 以上、 変化は避け難い ものだ。 さらに、一般消費者だけでなく、ワイン業界に携わる人々も、代替わり後の品質に関しては、 問答無用という厳しさ で接することも多い。 そういう私も、 ポジティヴとは言い切れない世代交代を何度も目にしてきた し、代替わり後にそのワインを全く購入しなくなったことも何度もある。 特に、 親がレジェンド級の造り手であった場合、後継者にかかるプレッシャーは相当なもの だ。 優れた造り手であった両親のもとに生まれた子供を、無条件で 「サラブレッド」 と表現したくなる気持ちはわかるが、 現実はそう甘くない 。 もちろん、この難しさを誰よりも理解しているのは、 造り手本人 だ。

梁 世柱
2024年8月3日


感性の世界 <オーストリア・シュタイヤーマルク特集:Part.2>
私は常に、 理性 でワインを探究してきた。 気候、土壌、地勢、葡萄品種がもたらす影響を マトリックス化 することによって、神秘のヴェールに覆われた テロワールを観測、分析可能なものとし 、そこに 栽培、醸造における人的要因も加え 、ワインに宿った特有のアロマ、フレイヴァー、ストラクチャーの根源に理路整然とした態度で向き合ってきたのだ。 ワインに対してそのようなアプローチを取り続けた理由は、単純化すれば 「理解したかったから」 の一言に尽きるが、 【結果には、すべて原因がある。】 というガリレオ・ガリレイの言葉を、幼い頃にその出自もコンテクストも知らずにどこかで聞きかじったまま、長い間盲目的に信じ込んできたのも一因と言えるだろう。 しかし、一般的にクラシック、もしくはオーセンティックと呼ばれるカテゴリーから探究範囲を大きく広げた結果、 様々な在り方のワイン との出会いを通じて、 私はこの世界に理性だけでは理解することができないワインが存在していることを認めざるをえなくなった。 理性でワインを探究してきたからこそ、その限界を知ることが

梁 世柱
2024年7月25日


ロゼ界のライジングスター、ロザリア。
ロゼワイン の歴史はかなり興味深い。 その 原初の姿 は、我々が知る 現代のロゼワインとは似ても似つかぬもの だったからだ。 最古の記録は 3,000年以上前の古代ギリシャ 。当時、 「ワインは水で薄めて飲む」 ことが上品とされていた。 白葡萄と黒葡萄を混醸して造った非常に薄い赤ワインのようなものを、さらに水で割る ことによって、ロゼワインらしきものとなっていたのだ。後に、赤ワインと白ワインらしきもの(現代のオレンジワインに近かった可能性が高い)に分けられるようにはなったが、数百年、いや、ひょっとすると数千年ほど、水で薄めたワインを飲んできた文化圏で、タニックな赤ワインや白ワインが市民権を得るには随分と時間がかかったようだ。

梁 世柱
2024年7月10日


美の真理 <オーストリア・シュタイヤーマルク特集:Part.1>
調和こそ美の真理であり、調和無き美は存在しない。 クラシックか、ナチュラルか。 探究を拒む人々によって二極化された世界観に興味を失ってから、随分と時が経つ。 固定された価値観の中で話をするのなら、私が探し求めている テロワール・ワイン は、 そのどちらでもなく、どちらでもある からだ。 美の対は破壊 であり、極端なクラシックもナチュラルも、極めて破壊的となり得るのだから、そこに美が宿らないのは必然である。 美とは理性的であると同時に、感性的でもある。 ワイン的表現をするのであれば、 理性的な美とは、天地、葡萄、人の総体 を意味し、 感性的な美とは、極限まで純化されたエネルギー となる。 理性的な美 は、 分析によって客観視 することができるが、 感性的な美は、極めて主観的 なものだ。 だからこそ、美の真理へと到達するためには、私自身が理性的かつ感性的であらなければならない。 シュタイヤーマルク地方 オーストリアの シュタイヤーマルク地方 を訪れた理由は、 テロワールという美の真理を追い求めていたから に他な

梁 世柱
2024年7月1日


ハプスブルグ風カジュアルペアリング
前回のペアリング研究室 では、西〜中央ヨーロッパ料理の粋と言える オーストリア料理 と、その象徴的な料理の一つである ヴィーナー・シュニッツェル の話をした。 今回もその流れのまま、もう一つの代表的なオーストリア料理である ヴィーナー・サフトグーラーシュ(ウィーン風ビーフグラーシュ) の話をしよう。

梁 世柱
2024年6月29日


再会 <63> Johannes Zillinger Part.2
Johannes Zillinger, Numen Rosé SL 2020. 偉大なロゼの探求 。 私が長年取り組んできた研究テーマの一つだ。 夏に、よく冷やしてカジュアルかつリーズナブルに楽しむ。 そのシチュエーション自体は私も楽しんでいるのだが、それだけ、となると流石に違和感を隠せない。 白ワイン、赤ワイン、スパークリングワインなら、カジュアルなものから、徹底してシリアスなものまで当然のように幅広く存在し、マーケットでもしっかりと棲み分けがなされている。 オレンジワインもおおむね同様の形となりつつある。 しかし、 ロゼだけはシリアスなものが極端に少ない 。

梁 世柱
2024年6月23日


オーストリアの大定番
ヨーロッパのワイン産出国は数多く訪れたが、カジュアルな食(ガストロノミーの話になると、国や地域ではなく、レストラン単位の話になる)の美味しさが際立っていると個人的に感じる国の2トップは、 オーストリアとポルトガル だ。 オーストリア料理 、と聞いてもイメージできる人は少ないかも知れないが、多民族国家であった ハプスブルグ王朝時代に、多種多様な食文化が融合し、磨き上げられた 結果、非常にバランス感に長けた料理体系として発展したという経緯がある。 言うなれば、 西〜中央ヨーロッパ料理の粋 、とも言えるのがオーストリア料理なのだ。 さらに、オーストリア料理は温かい料理が、 ちゃんと「温かく」提供される 、という日本人(アジア人)には特に嬉しい特徴もある。 さて、オーストリア料理の中でも、最も象徴的なものとされる料理の一つが、 ヴィーナー・シュニッツェル 。

梁 世柱
2024年6月23日


再会 <62> Johannes Zillinger Part.1
Johannes Zillinger, Parcellaire Blanc No.1 2021. オーストリア は、世界でも有数の ナチュラルワイン銘醸地 だ。 北海道とほぼ同じ国土面積、大阪府とほぼ同じ総人口。オーストリアはとても小さな国であるため、ここでいうナチュラルワイン銘醸地としての姿は、 物量によるものではなく、圧倒的な質の高さによって獲得した評価 である。 特に、Steiermark(シュタイヤーマルク)とBurgenland(ブルゲンラント)には、世界最上クラスと目されるナチュラルワイン生産者達が名を連ねる。 ルドルフ・シュタイナーがオーストリア(オーストリア=ハンガリー帝国)の生まれであることも、かの国でビオディナミ農法に真摯に取り組む造り手が相対的に多い理由の一つとなっているかも知れないが、それ以上に 生真面目でやや内向的な(ここが重要なのです)国民性 が、モノづくりの質を限りなく高めていると考えた方がしっくりとくる。

梁 世柱
2024年6月9日


ノイジードル湖西側の至宝、ルスター・アウスブルッフ
ノイジードル湖東側、Illmitz(イルミッツ)周辺で造られる貴腐ワインの魅力に関しては、 別稿 にてレポートしたが、 西側のRust(ルスト) にもまた、ヨーロッパのワイン史にその名を残す偉大な貴腐ワインがある。 Ruster Ausbruch(ルスター・アウスブルッフ) だ。 東側にはKracherやNittnausなど、貴腐ワイン生産者としてはかなりの規模となる大手がいるため、知名度や入手のし易さにおいては大きくリードされているが、より希少となるスター・アウスブルッフにもまた、異なった魅力が宿っている。

梁 世柱
2024年6月7日


ノイジードル湖の魔法
世界三大貴腐ワイン といえば、 ドイツのTBA、ハンガリーのトカイ 、そして フランス・ボルドーのソーテルヌ だが、 オーストリア・ブルゲンラントのノイジードラーゼー を含めて「世界四大」とされてことかったことに、何か特別な理由があるのか、かねてから興味があった。 ノイジードラーゼー (本稿ではノイジードル湖の東側を意味する。西側のRuster Ausbruch DAC は条件が異なる。 )は前述した3産地と同じく、(ほぼ毎年と言えるほど) 安定して貴腐ワイン造ることができる場所 だからだ。 このような場所は、ワイン産地として形成されているという意味では、 世界にこの4ヶ所しか無い のだから、四大となっていないことに違和感が生じる。 確かにノイジードラーゼーの価格は安いが、ソーテルヌにもトカイにも安いワインはある。 甘口ワイン産地としての歴史は500年以上もあるので、「格式」という意味でも問題はない。

梁 世柱
2024年5月30日
bottom of page